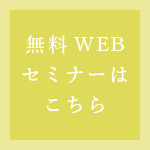こんにちは。MTI(マッサージセラピー・インスティテュート)学長の國分利江子です。
今日は首凝りや頭痛の新しいアプローチについてお伝えします。多くの方が悩まれるこの症状に対して、従来とは異なる視点から効果的な施術方法をご紹介します。
動画も併せてご覧ください。
首凝り・頭痛の悩みを緩和するマッサージセラピー講座
首凝りと頭痛の原因は必ずしも首や頭部にあるわけではない
首凝りや頭痛でお悩みの方が来られた時、多くのセラピストは首や肩に直接アプローチします。ところが、その症状の原因が実は別の場所にあるケースが少なくありません。
私がアメリカのニューヨークにあるスウェーディッシュ・インスティテュートで学生だった頃、筋肉学を学んでいました。筋肉学では関節ごとの筋肉の起始停止作用を学び、姿勢分析から施術プランを作ります。その先にある「筋膜アプローチ」が今日お伝えしたいポイントです。
筋膜アプローチの重要性
筋膜は今や多くのセラピストが注目していますが、この筋膜を理解するためには、まず筋解剖学の基礎知識が不可欠です。語学でいえば、いきなり英語の文章を書くのではなく、アルファベットや単語から学ぶようなものです。セラピストの仕事も筋解剖学からスタートし、そこから筋膜での分析へと進みます。
スウェーディッシュ・インスティテュートで学んでいた時、ハリウッドの有名女優さんの頭痛が従来のあらゆる施術(鍼、カイロプラクティック、オイルマッサージ、整体、運動療法など)で改善しなかったケースに出会いました。その原因は驚くべきものでした。
仙骨からのアプローチ
首凝りと頭痛の改善には、仙骨がポイントになることがあります。筋膜の流れは前頭骨から後頭骨へと向かい、そこから脊中起立筋を通って仙骨まで続いています。この筋膜の流れに沿った施術が効果的なのです。
具体的には、うつ伏せの姿勢で後頭骨の上項線(後頭稜)から施術を始めます。この時、骨に直接圧をかけるのではなく、筋肉と筋膜の厚みに指を入れます。まるでブルドーザーで土を掻き分けるように、筋膜を動かしていきます。
高度な施術テクニック
この施術には「ボディメカニクス」の理解が必須です。指に力を入れず、骨を押さないようにしながら、筋膜と筋肉にしっかりと圧をかける技術は、上級者向けのアドバンステクニックです。
首の両側に拳を置く際も注意が必要です。首を下に押してはいけません。呼吸が苦しくなったり不快になる可能性があります。後頭骨から拳の小指側で筋膜を押さえるように、斜めに圧をかけることがポイントです。
施術を続けると、僧帽筋筋膜から仙骨へと圧を移動させていきます。ここでも骨を押さないよう注意し、筋膜と筋肉の厚みにだけ圧をかけます。さらに高度なテクニックとして、圧をかけながら腕を使って筋肉の位置をずらし、筋膜の癒着を解消する方法もあります。
最後に、ピンポイントのワークで熱を作り出し、筋膜の状態を変えていきます。緊張して固まった状態から、本来の伸びやかでしなやかな形に戻るのです。
まとめ
首凝りや頭痛の原因が仙骨まで続く筋膜の緊張にあることがあります。脊中起立筋群の緊張が首に負担をかけ、それが頭部を経て前頭部まで達することで頭痛を引き起こすのです。
この施術法はボディメカニクスの理解が重要で、実際に見て学ぶことで効果的に習得できます。皆さんもこの方法を試してみてください。リアルセミナーでは、より詳しい技術をお伝えしています。筋解剖学の基礎をしっかり学び、効果的な施術ができるセラピストを目指しましょう。
より詳しい情報を知りたい方は、公式LINEにぜひご登録ください。限定WEBセミナーやMTIの情報をお届けしています。皆さんのセラピストとしての成長を心から応援しています。
【公式LINE登録はこちら】
次回のブログでお会いしましょう!